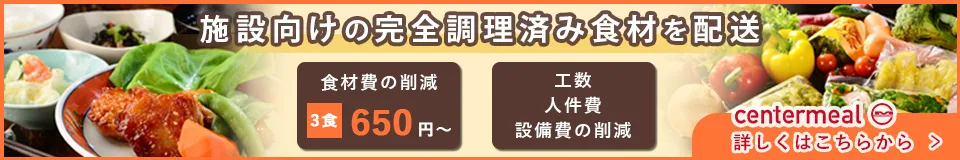「軟菜食の特徴とは?」
「軟菜食を作る際のポイントは?」
「軟菜食のおすすめメニューが知りたい」
一口に「介護食」といっても、その種類は多種多様です。
本記事では、介護食のなかでも普通食と同様に楽しめることで人気の「軟菜食」について、詳しく解説していきます。
安くておいしい3食650円~センターミールのサービスについてはこちら >
目次
軟菜食とは?

軟菜食(なんさいしょく)は、普通食の食材を圧力鍋や長時間調理することで柔らかく調理して、歯のない方でも美味しく食べられる食事です。
見た目や風味は普通食とほとんど変わりません。
また、軟菜食をペースト状につぶして、とろみ剤で形を整えた「ソフト食」というものも介護食のひとつとして知られています。
【関連記事】ソフト食とは?メリットやデメリットと作り方のポイントを解説
軟菜食の特徴
次に、軟菜食の特徴を2つに分けて解説します。
舌や歯茎で食事ができる程度の柔らかさがある
軟菜食の特徴のひとつは、舌や歯茎で食事ができる程度の柔らかさです。
食材は圧力鍋や長時間の調理によって柔らかくなり、噛む必要が少なくなります。
これにより、歯のない方や咀嚼が困難な方でも、口内摂取することが容易になります。
柔らかさと食材の風味を活かした、快適で美味しい食事が提供されます。
普通食と同様に食事を楽しめる
軟菜食の特徴のひとつは、普通食と同様に食事を楽しむことができることです。
食材をただ柔らかく調理する軟菜食は、見た目や風味にほとんど変化がなく、味わい深い食事が体験できます。
歯のない方でも、無理なく美味しく食べることができるわけです。
軟菜食は、安心して摂取できる柔らかな食事である一方で、食事の喜びや満足感を与えるとして多く人々に利用されています。
軟菜食がおすすめの方

ここからは、軟菜食がおすすめの方を紹介していきます。
以下4つに当てはまる方は、前向きに検討してみてください。
- 歯の状態が良くない方
- 噛む力が弱い方
- 食べ物を飲み込むのが困難な方
- 胃もたれしやすい方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
歯の状態が良くない方
歯の状態が良くない方、あるいは歯がない方にも、軟菜食がおすすめです。
柔らかく調理された食材は咀嚼が少なくて済み、歯に負担をかけずに食事ができます。
さらに、歯茎や口内の刺激も少ないため、痛みやトラブルを軽減できます。
軟菜食は食事の摂取を容易にし、歯の健康をサポートする選択肢といえるでしょう。
噛む力が弱い方
噛む力が弱い方にも、軟菜食がおすすめです。
柔らかく調理された食材は少ない咀嚼で食べることができ、噛む力の問題を解消します。
食材の粒度や柔らかさを調整し、食事を摂る際の負担を軽減します。
軟菜食は、噛む力が弱い方でも食事を楽しむことができる健康的な選択肢です。
食べ物を飲み込むのが困難な方
食べ物を飲み込むのが困難な方にも、軟菜食がおすすめです。
柔らかく調理された食材は飲み込みやすく、喉に詰まるリスクを軽減します。
食材の質感や形状も考慮し、食べやすい状態に調整する軟菜食は、食事の安全性を向上させ、食べ物を飲み込む難しさを軽減する方法として効果的です。
胃もたれしやすい方
実は胃もたれしやすい方にも、軟菜食がおすすめです。
柔らかく消化しやすい食材は、胃に負担をかけずに食事ができます。
また、軟菜食では脂肪や油分の摂取も制限されるため、胃もたれを起こしにくくなります。
軟菜食は胃もたれしやすい方にとって、軽い胃の快適さを提供する食事スタイルといえます。
軟菜食を作る際のポイント

ここからは、軟菜食を作る際のポイントを見ていきます。
主なポイントは、以下の4つです。
- 柔らかく仕上げる
- 液体にはとろみをつける
- 刺激物は避ける
- 食べやすい形状にする
それぞれ解説します。
ポイント①柔らかく仕上げる
軟菜食を作る際のポイントは、食材を柔らかく仕上げることです。
煮る、蒸す、炊くなどの加熱方法で食材を柔らかくすることで、噛む力の弱い方でも食べやすくなります。
また、包丁を使って細かく切ったり、ミキサーを使って砕いたりすることも柔らかさを生み出すポイントです。
食材の柔らかさは、軟菜食の魅力を引き出すために重要です。
ポイント②液体にはとろみをつける
軟菜食を作る際のポイントは、液体にとろみをつけることです。
とろみをつけることで、食材やスープが滑らかな食感になり、飲み込みやすくなります。
ゼラチンや専用のとろみ剤を使ってとろみをつける方法が一般的。
液体にとろみをつけることで、軟菜食をより食べやすくすることができます。
【関連記事】介護食に必要なとろみとは?とろみをつける際のコツも紹介
ポイント③刺激物は避ける
軟菜食では、刺激物を避けることが重要です。
辛い調味料や刺激的な食材は消化器官に負担をかける可能性があります。
代わりに、やさしい味付けや優しい調味料を選ぶことで、食べやすく安全な食事を提供できます。
刺激物を避けることで、軟菜食を受け入れやすくなります。
ポイント④食べやすい形状にする
軟菜食を作る際、食べやすい形状にすることも大切です。
食材を柔らかく調理し、切りやすい大きさにすると噛む力の低下している方でも食べやすくなります。
また、つぶす・すりつぶすなどの調理法を用いることで、消化しやすくなります。
形状を工夫することで、軟菜食をより快適に摂ることができるでしょう。
軟菜食におすすめしない食材
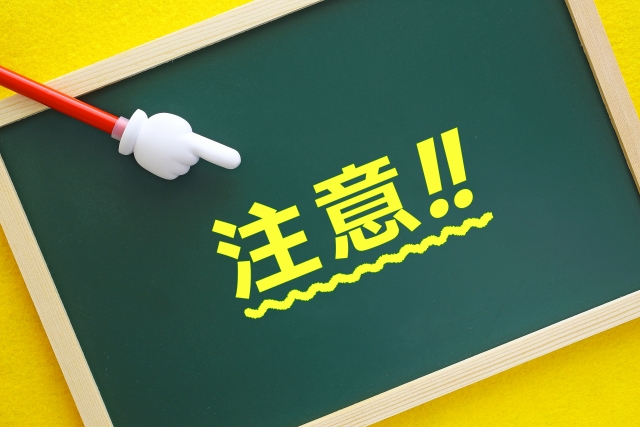
次に、軟菜食におすすめしない食材も解説していきます。
以下の4つの食材は注意が必要です。
- 生野菜
- 繊維が多いもの
- 口内の水分が取られるもの
- 張りつきやすいもの
それぞれ確認してください。
生野菜
生野菜は軟菜食におすすめしません。
というのも、生野菜は噛む力が必要であり、消化しにくい可能性があるからです。
加熱調理によって野菜を柔らかくするか、野菜ジュースやスープにすることで、栄養素を摂取しながら消化の負担を軽減することが大切です。
繊維が多いもの
根菜類などの繊維が多い食材も、軟菜食におすすめしません。
これらの食材は固くて噛みにくいため、消化に負担をかける可能性があります。
調理する際には、柔らかくなるまで加熱するか、野菜ジュースやピューレ状にすることで消化しやすくなります。
軟菜食には注意が必要な食材です。
口内の水分が取られるもの
パンなどの口内の水分を取られる食材も、軟菜食におすすめしません。
これらの食材は乾燥しており、嚥下や消化に困難をもたらす可能性があります。
柔らかく湿った食材を選び、水分摂取に注意することが大切です。
軟菜食には適した食材を選びましょう。
張りつきやすいもの
海藻類などの張りつきやすい食材も、軟菜食には適していません。
これらの食材は口内に張りつきやすく、摂取後の嚥下困難や窒息のリスクがあります。
柔らかくしたり、小さく切ったりしてから摂取するか、柔らかい食材を選んで食べることが重要です。
安全に食事を楽しむために注意しましょう。
軟菜食のおすすめメニュー

最後に、軟菜食のおすすめメニューを3つご紹介します。
どれも簡単で、美味しいものばかりです。
メニュー①うどん
うどんは柔らかく、優れた食物繊維と炭水化物を含んでおり、軟菜食におすすめのメニューです。
柔らかい食感で嚥下しやすく、消化にも負担をかけません。
具材を工夫することで栄養バランスも整えられます。
軟菜食を楽しむならうどんはおすすめです。
メニュー②果物のコンポート
果物のコンポートは、柔らかくて甘みのある果物を煮込んだデザートです。
嚥下しやすく消化にも負担をかけません。
フレッシュな果物の栄養を楽しむことができ、食事のバリエーションも広がります。
柔らかい食材を楽しみたい方におすすめです。
メニュー③野菜のごま和え
野菜のごま和えは、柔らかくて簡単に作れる軟菜食のメニューです。
柔らかい野菜をごまだれで和えることで、栄養豊富な食事が楽しめます。
ごまの風味と野菜の食感が絶妙で、食欲をそそります。
消化にも優れ、健康的な食事の一部としておすすめです。
軟菜食とは普通食と変わらない楽しみが得られる介護食

今回は、軟菜食について解説してきました。
軟菜食は、嚥下や消化に難がある人々のための介護食ですが、普通食と変わらない楽しみを得ることができます。
柔らかく加工された食材を工夫して使用することで、味や食感が充実しており、食事の楽しみを損なうことがないでしょう。
栄養バランスも考慮された安全で美味しい食事といえます。